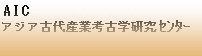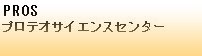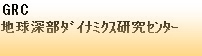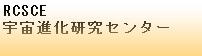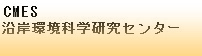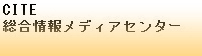広島大学より以下のとおり案内がありましたのでお知らせします。
———————————————————————————
研究者のみなさまへ(English follows Japanese.)
本フォーラムでは5人の若手研究者がそれぞれの将来の研究課題のために今議論すべきと考える超領域的なトピックを掲げ、カールスルーエ工科大学、ハイデルベルグ大学の研究者とともに対話を行います。関心のあるトピックを選んでぜひ議論にご参加下さい。分野と文化圏を超えた新たな繋がりが見つかるかもしれません。
◆◆◆ 開催概要 ◆◆◆
【開催日時】2021年11月23日(火)17:30(日本時間)/ 9:30(中央ヨーロッパ時間)
【開催形式】オンライン開催(Zoom)
【使用言語】英語(同時通訳無し)
【登壇者/テーマ】
■ 山本 暁久(第2期フェロ―)
Quantification, control, and modeling of mechanical and dynamical alteration of
cell and tissue towards detection and mechanistic understanding of disease
■ 本郷 峻 (第2期フェロ―)
What research do we need to do to reconcile the conflicts between biodiversity
conservation and food security in developing countries?
■ 田中 智大(第1期フェロー)/Carolin Klonner
What engineering research is expected from society in this “full-of-informatics”
(e.g. AI, Drone, ICT) era? Any research field in the similar situations?
■ 藤井 俊博(第1期フェロー)/Iryna Lypova/Markus Roth
Clarifying the most energetic particles in the universe
■ 藤井 悠里(第2期フェロ―)/Georg Lars Hildenbrand
How and where did life emerge? What did the first life looked like? Is it possible
to have other form of life?
【HeKKSaGOn発展プログラム】
次世代の学術を担う研究者が、若手時代から国際的かつ世代を超えた特別な繋がりを持ち、縦横無尽に羽ばたく基盤を形成することを応援するプログラムです。
HeKKSaGOn [ ヘキサゴン: 日独6大学アライアンス ] の枠組みにおいて醸成してきた日独大学間の良好な関係性から展開する新たな取り組みでもあります。
【参加申込フォーム】https://forms.gle/iauSWDHzz1Kji5UL9
【申込期限】2021年11月22日(月)
【フォーラムHP】http://www.l-insight.rp.kyoto-u.ac.jp/ja/event/1689/
【問合せ先(Contact)】
京都大学 次世代研究創成ユニット
Center for Enhancing Next-generation Research, Kyoto University
TEL: +81-75-753-5916
E-mail:admin-l-insight@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
================ English Message===============
This forum supports next generation of researchers in forming special international and inter-generational connections early in their careers in the hope of creating foundations for them to excel. This is a new initiative that has spined-off from the friendly relationship between German and Japanese universities fostered through the HeKKSaGOn (The German-Japanese University Alliance) framework, which is now in its eleventh year.
Researchers from Kyoto University, Heidelberg University, and Karlsruhe Institute of Technology will gather to discuss five topics proposed by several fellows from L-INSIGHT, a community of early career researchers at Kyoto University.
The fellows believe that these trans-disciplinary topics including research environments and ways of thinking in other spheres of research are important in discussing the development of their future research.
We cordially invite you to the discussions regarding the topics of your choice.
Please sign up now to find your new and future connections through this opportunity.
【Spin-off programme from HeKKSaGOn“Five Dialogues for Future Research and Science with Early Career Researchers”】
Speakers/Topics
YAMAMOTO Akihisa
Quantification, control, and modeling of mechanical and dynamical alteration of cell and tissue towards detection and mechanistic understanding of disease
HONGO Shun
What research do we need to do to reconcile the conflicts between biodiversity
conservation and food security in developing countries?
TANAKA Tomohiro/Carolin Klonner
What engineering research is expected from society in this “full-of-informatics”(e.g. AI, Drone, ICT) era? Any research field in the similar situations?
FUJII Toshihiro/Iryna Lypova/Markus Roth
Clarifying the most energetic particles in the universe
FUJII Yuri I./Georg Lars Hildenbrand
How and where did life emerge? What did the first life looked like? Is it possible to have other form of life?
Date/ Time: 23 November (Tuesday) 2021, 17:30(JST) | 9:30(CET)
Venue: Online(Zoom)
Registration Form: https://forms.gle/iauSWDHzz1Kji5UL9
Language: English
See more details on our website: http://www.l-insight.rp.kyoto-u.ac.jp/en/event/1692/
プログラム詳細チラシ
http://web.office.ehime-u.ac.jp/renraku/file/31554l-insight_fly_211105-6_3p.pdf